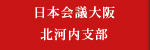- 鎮座地
-
大阪府寝屋川市仁和寺本町4-11-29
- 御祭神
-
菅原道真、伊弉諾尊、伊弉冉尊、藤原藤房
- 祭日
-
10月18日
- 由緒
-
当神社は、元からここに鎮座されたのではなく、延宝二年(一六七四)六月十六日の淀川の仁和寺堤防が決壊して、社殿が流され村の田畑は皆川砂を冠ったもので、その上砂を村の中央に集めて耕地の復旧を図り、その砂山の地に新たに社殿を造営し、神様をお移ししたものである。
元の鎮座地は字本宮(もとみや)と称し、田ん圃の中に、籬で囲った石碑が建っている。
ここが、もとの「氏神社」の建っていた所である。その石碑には、「仁和寺氏神社御本地 代々能人敬う神乃宮之跡」と刻まれている。そして傍らに小さな石の祠がある。
旧社の起源は、伝うるところによると、仁和寺庄に観音寺(※)の建立されると同時に、本宮の地に建てられた白山権現であるとされている。元の産土神は今古宮と称して境内摂社に奉祭する白山権現(祭神・伊弉諾尊・伊弉冉尊)であった。寛永十年(一六三三)永井信濃守が当地方の領主となり、領内の産土神に菅原道真を祭ってよりは当社の主神として天満宮・白山権現とならべ称えることになった。
明治五年、当社は村社に列せられたが、明治四十四年一月十四日、燐村の佐太天神社に合祀されて表向きは佐太天神の御旅所となっていた。
昭和になって間もなく神様に戻ってもらう気運が湧き、昭和四年以降内務省に、村を挙げて神社復旧運動を起こし、それが正式に復旧を許可されたのは太平洋戦争のさなか昭和十八年七月二十六日付けであり、その翌月の八月二十五日、盛大な還幸祭を執り行い、長い間の村民の願いは達せられた。
仁和寺地区のほぼ中央にあって、大木が茂り、鎮守の森としての威容を備え、この神社ならではの感がある。※観音寺の創建者 敦實親王(あつみのしんのう)宇多天皇の皇子八九三生~九六七没